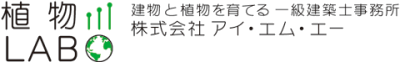瓢箪加工(No.331)の後編です
極小瓢箪をプランターや植木鉢などを使い自宅の軒下で栽培して、もう数十年になりますが、‘これは良い’と言う姿の瓢箪はなかなか出来ません。でも沢山出来る瓢箪の中に毎年‘あ!’と言う良い姿のものが現れるのです。何が作用しているのか分かりませんが、これも自然相手の楽しみです。
 △水に漬けて2週間ほど経過した瓢箪の様子を見ながら、外の水道排水口で袋から出した様子です。表皮がうっすらと浮き上がっているぐらいが丁度よいタイミングです。漬けすぎると表皮が腐敗して匂いがきつくなるので、その直前がベストです。
△水に漬けて2週間ほど経過した瓢箪の様子を見ながら、外の水道排水口で袋から出した様子です。表皮がうっすらと浮き上がっているぐらいが丁度よいタイミングです。漬けすぎると表皮が腐敗して匂いがきつくなるので、その直前がベストです。
 △これが表皮の浮き上がった状態の瓢箪を拡大して見た写真です。この薄皮をそうっと剥がして、下の中皮に傷をつけないように丁寧な作業が必要です。一つひとつ水道水をかけながら水圧で剥いて、最後は手で丁寧に薄皮を剥いでいきます。
△これが表皮の浮き上がった状態の瓢箪を拡大して見た写真です。この薄皮をそうっと剥がして、下の中皮に傷をつけないように丁寧な作業が必要です。一つひとつ水道水をかけながら水圧で剥いて、最後は手で丁寧に薄皮を剥いでいきます。
 △これが薄皮を取り除いた状態の極小瓢箪です。洗濯バサミは瓢箪の大きさをイメージしてもらうために並べました。この状態で1~2週間風の通る所で干し上げれば、瓢箪素材の完成です。日陰で干せば白く、日に当てれば小麦色の瓢箪になります。
△これが薄皮を取り除いた状態の極小瓢箪です。洗濯バサミは瓢箪の大きさをイメージしてもらうために並べました。この状態で1~2週間風の通る所で干し上げれば、瓢箪素材の完成です。日陰で干せば白く、日に当てれば小麦色の瓢箪になります。
〇次回は冬支度前のイチゴ苗たちを見てみましょう